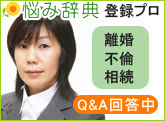〒223‐0061 神奈川県横浜市港北区日吉1丁目7番43号
営業時間 | 9:00~18:00 |
|---|
定休日 | 土日祝祭日 |
|---|
別居中に無断で配偶者の住居に立ち入ると問題になる?
離婚を前提に、家を出て妻と別居しているけど、置いてきてしまった荷物があるので取りに帰りたい。
妻と顔を合わせるのは気まずいから、妻がパートで留守にしている時間帯を狙って一度家に帰ろうと思っています。鍵は持っていますし、この家は自分の所有です。この場合、何か問題があるでしょうか。
結論から申し上げて、たとえ夫婦であっても、別居中に無断で相手の住居へ立ち入ると、※住居侵入罪に問われる可能性があります。
※刑法130条 (住居侵入罪)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
「住居」とは、人が居住したり日常生活を営んでいる場所です。
一軒家はもちろん、アパートやマンションの一室も、「住居」ということになります
また、「侵入」とは、居住者(住居権者)の意思に反して、住居に立ち入ることです。
すなわち、住居侵入罪は「居住者」を保護するものであり、「所有者」を保護するものではないため、居住者の意思に反していれば、住居侵入にはなります。
とはいえ、ご相談のような事例の場合には、「別居中とはいえまだ夫婦であり、しかも所有者なんだから問題ないのでは?」と考える方もいると思います。
しかしながら、別居している場合には、こういった事例でも住居侵入罪が成立するという裁判例も存在するところです。十分注意が必要でしょう。
東京高等裁判所昭和58年1月20日判決(判例時報1088号147頁)は、別居して離婚訴訟中の妻が居住する夫所有の家屋へ、夫が合鍵を使って入った行為について、住居侵入罪の成立を認めました。
トラブルに発展する可能性もあるので、別居をする場合は、別居合意書を作成し、約束事を明記しておくことをおすすめします。
女性行政書士が親切丁寧な対応をさせていただきます。
東京 神奈川(横浜) 千葉 埼玉 東横線沿線を中心に別居合意書の作成をさせていただきます。
公正証書の作成もお手伝いさせていただきます。
婚姻費用の分担〜夫が住宅ローンを負担している場合は考慮される?
最近では夫婦関係を見直すため別居をされるご夫婦もいらっしゃいます。
夫が家を出て、妻と子供がそのまま自宅に残る。
夫は妻に婚姻費用を支払い、住宅ローンもそのまま夫が支払う。
そんな選択をするご夫婦も多いかと思います。
このようなケースの場合、婚姻費用の算定にあたって、夫の支払っている住宅ローンはどのように考慮されるのでしょう。
色々考え方はありますが、ここでは一つの方法をご紹介します。
先ずは婚姻費用算定表に従って、夫が負担すべき婚姻費用の額を算出します。
この算定表は権利者(妻側)の住居費は特別経費として考慮されていますが、妻が自宅に残る場合、妻はこの住居費を免れていることになります。
その一方で夫は、住居費も負担し、住宅ローンも負担することになり二重の負担を強いられることになりますので、この住居費を考慮しなければ不公平ということになります。
そこで算定表から導かれた婚姻費用から一定額を控除するということになります。
では、一体どのような額を控除すればよいのでしょう。
これもまた色々考え方はありますが、一つご紹介します。
控除する額を、判例タイムズ1111号294ページ資料2において示されている権利者(妻)の実収入に対応する標準的な住居関連費とするものです。
この表に従うと、平均的な住居費56,515円ですが、収入によって以下のとおりの額になります。
0〜1,999,999円の場合 27,940円、
〜2,499,999円の場合 32,354円
〜2,999,999円の場合 31,655円
〜3,499,999円の場合 32,590円
ですので婚姻費用分担表で算出された婚姻費用額からこの標準的住居費を差し引くことで調整していくことになります。
婚姻費用が決まりましたら、確実に支払ってもらえるよう別居合意書(婚姻費用分担の契約書)を作成するとよろしいでしょう。
不払いの場合に備え、別居合意書を強制執行認諾条項付公正証書にすることをお勧め致します。
別居合意書についてご不明な点があれば是非ご相談ください。
女性行政書士が親切丁寧な対応をさせていただきます。
東京 神奈川(横浜) 千葉 埼玉 を中心に別居合意書を作成させていたただきます。
公正証書の作成もお手伝いしております。
不貞の示談書~違約金条項を付けられる?
配偶者に不貞行為があって、不貞の相手方と示談をする際、慰謝料の支払のほかに、次に不貞行為に及んだときはペナルティを課したい、というご希望を伺うことが多くあります。
このようなペナルティ(違約金)の約束をすることは可能なのでしょうか。
結論から申し上げますと、可能です。
ただし、違約金の額は妥当な額にする方が得策でしょう。
違約金というのは、約束違反をした場合に支払うと約束したお金のことです。
法的にいいますと、約束違反(=債務不履行)により発生する損害賠償額を予め定めておく、というものです。(民法420条1項・3項)
具体的には、「次に不貞行為をした場合、違約金として300万円を支払う」という約束です。
このように、再度不貞行為に及んだ場合のペナルティを課しておけば、二度と不貞行為をしないという抑止力になります。
特に配偶者に不貞行為があっても離婚しない、できない、と考え夫婦関係の再構築を希望している場合は、心強いお守りになるでしょう。
ただ、やはり注意しなければならないのは、その金額です。
違約金の額はあくまで違約の条項の担保として相当な範囲に限られ,それを越える範囲の金額は公序良俗に反し無効となる可能性が高いです。
参考になる裁判例をご紹介します。
平成25年12月4日判決 東京地方裁判所
【事案の概要】
原告(男性)が、原告の妻と不貞行為に及んだ被告を訴えた事案です。
原告の妻と被告は会社の部下と上司という間柄であり、探偵による調査の結果、二人は不貞関係にあることが判明しました。原告は被告を呼び出し、原告の妻との連絡や接触を禁止すること、及びこれに違反した場合には違約金1000万円を支払うことを内容とする誓約書に署名をすることを求め,被告は誓約書に署名をしました。
その後、原告の妻からのメールをきっかけに不貞関係が継続されることになり、原告が依頼した探偵調査により再度の不貞行為が発覚しました。
そこで原告は被告に対し、再度の不貞行為に対する慰謝料と違約金条項に違反したことに対する損害賠償を求めて訴えを提起しました。
裁判所の判断
本件違約金条項は、面会・連絡等禁止条項違反について、違約金を課すものであると認められるところ、違約金は損害賠償額の予定と推定されるから(民法420条3項)、その額については、面会・連絡等禁止条項が保護する原告の利益の損害賠償の性格を有する限りで合理性を有し、著しく合理性を欠く部分は公序良俗に反するというべきである。
本件違約金条項による違約金1000万円は、損害賠償額として著しく過大であるというほかない。面会・連絡等禁止条項に違反した場合の損害賠償額は、その態様が悪質でもせいぜい50万円ないし100万円程度と考えられるから、履行確保の目的が大きいことを最大限考慮しても、少なくとも150万円を超える部分は、違約金の額として著しく合理性を欠き、公序良俗に反し無効である。
この裁判例を参考にすると、著しく過大な違約金条項でも、全部が無効になるわけではなく、妥当な範囲を超える部分が無効になる。
また、妥当な金額としては、50万円から100万円、高くてもせいぜい150万円とみているようです。
婚姻費用の算定〜高額所得者の場合は?
婚姻費用というのは、夫婦が資産、収入に応じた結婚生活を維持するのに必要な費用のことをいい、婚姻費用を夫婦のどちらがどのように負担するのかについては、まずは当事者の協議等により決めることになります。
当事者間の話し合いや調停で協議が整わないときは、家庭裁判所が当該夫婦の資産、収入、その他一切の事情を考慮して審判により決定することになります。
婚姻費用分担額の算出式は、実費方式、生活保護基準比率方式等いくつかありますが、養育費同様婚姻費用についても簡易迅速な算定が可能になるよう、東京と大阪の裁判官らで構成する「東京・大阪養育費等研究会」が標準算定方式を発表しています。
また、併せて、この算定方式に基づく婚姻費用算定表が発表されており、全国の家庭裁判所でもこの算定表が広く利用されています。⇒婚姻費用分担表
ただ、この標準算定方式、権利者の収入については、給与所得者年収1000万円以下、事業所得者年収710万円以下、義務者の収入については、給与所得者年収2000万円以下、事業所得者年収1409万円以下を前提とするものであり、義務者の収入が2000万円(給与所得者を前提)以上の場合については、個々の裁判官の判断に委ねられています。
収入が2000万円を超えるような場合について、文献においては、以下のような方法が紹介されています。
① 標準算定方式を修正するなどして利用方法
a 標準算定方式の収入2000万円を上限とする方法
b 基礎収入を算定し、これを生活費指数で按分するが、基礎収入の割合を修正する方
法
c 基礎収入を算定し、これを生活費指数で按分するが、基礎収入の算定において貯蓄率
を控除する方法
② 同居中及び現在の生活状況から算定する方法
この点、
収入が標準算定方式の収入額の上限を年額500万円程度超える場合は①aの方法を、これより高額の場合は①bや①cの方法を、さらに高額で億単位の収入であったり、生活状況が標準的な世帯と著しく異なる場合には②の方法に依るべきとするものがあり、専ら、各事案の個別的事情を考慮して認定するのが相当としています。ただし、これまでの審判例等から月額100万円を超えることはないとしています。.
裁判例
妻が別居中の夫に対して婚姻費用の分担を求めた事案
義務者(夫)の年収1億5320万円、権利者(妻)年収0円
原審では月額120万円ないし125万円としたところ、これを不服とした夫が抗告し、これに対し妻は152万円ないし157万円と定めるよう求めた。
裁判所は、
一般に、婚姻費用の額は、いわゆる標準方式を基本として定めるのが相当であるが、本件は義務者の年収が標準方式の上限をはるかに上回っており、標準方式を応用する手法によって婚姻費用分担金の額を算定することは困難であるとして、義務者と権利者の同居時の生活水準、生活費支出状況等及び別居開始後の権利者の生活水準、生活費支出状況等を中心とする諸般の事情を踏まえ、家計が2つになることにより双方の生活費の支出に重複的な支出が生じること、婚姻費用は従前の贅沢な生活をそのまま保障しようとするものではないこと等を考慮し、月額75万円の支払いを命じた。(ただし、夫は妻の住居の賃料月額330万円を負担することが前提となっている。)
東京高等裁判所平成29年12月15日 決定
出典 家庭の法と裁判 19
別居するにあたって準備することは?
夫婦関係が破綻の危機に瀕している場合、相手との冷却期間を設けるため、別居という選択をするご夫婦も多いかと思います。
別居にあたって、事前に準備しておいた方がいいことは何でしょう。
1.生活費の確保
まずは、別居中の生活費の確保でしょうか。
別居期間中でも夫婦間で婚姻費用の分担義務(民法760条)があります。
ですので、収入が多い方が少ない方に婚姻費用(生活費)を渡す必要があります。
別居後に婚姻費用を請求するのであれば、相手方の源泉徴収表や月々の支出を明らかにする資料などを準備するとよろしいでしょう。
もし相手方との協議が可能であれば、別居前に婚姻費用として具体的な金額を取り決めてもよいと思います。相手が納得すれば強制執行認諾条項付公正証書を作成しておいてもよいでしょう。
その他お子様との面会交流や別居中の決まり事など決めておかれてもよろしいでしょう。
別居合意書はこちらを参考にしてください。⇒別居合意書
2.不貞の証拠
もし、あなたが別居の先に離婚を見据えているのであれば、離婚を有利に進めるための証拠を確保できると安心です。
別居してからでは証拠を得るのは難しいことが多いので、不貞行為が疑われるのであれば事前にその証拠を集めるようにするとよろしいでしょう。
3.財産の把握
また、財産分与も念頭に置く必要があります。
財産分与は別居時点の夫婦共有財産が対象になります。
別居時点での預金などの財産状況はできるだけ把握しておきましょう。
別居合意書についてご不明な点があれば是非ご相談ください。
女性行政書士が親切丁寧な対応をさせていただきます。
東京 神奈川(横浜) 千葉 埼玉 を中心に別居合意書を作成させていたただきます。
公正証書の作成もお手伝いしております。
別居に際して持ち出した財産の処遇は?
妻が突然家を出て現在別居中です。
その際、私の給与が振り込まれていた口座の預金通帳とカードを勝手に持ち出していました。
この預金が財産分与の対象だということは分かっているけれど、まだ離婚も決まったわけではないのに勝手に持ち出すのは納得がいかない。
この預金を取り返すことは出来るか、というご相談を受けることがあります。
結論から申し上げますと、取り返すのは難しいでしょう。
しかし、この預金は離婚時の財産分与で清算されることになろうかと思います。
ただし、この財産が婚姻費用として費消された場合、その額が適正な範囲内であれば財産分与の対象財産から除外されることになります。
この相談のように、別居に際して、一方が現金や預貯金を持ち出すことはしばしばあり、これに対し相手方は不法行為による損害賠償請求や不当利得返還請求の訴訟を提起して返還を求めていくことがあります。
裁判所は以下のように判示してその請求を認めていません。
「夫婦の一方が婚姻中に他方の協力の下に稼働して得た収入で取得した財産は、実質的には夫婦の共有財産であって、性質上特に一方のみが管理するような財産を除いては、婚姻継続中は夫婦共同で管理をするのが通常であり、婚姻関係が破綻して離婚に至った場合には、その実質的共有財産を清算するためには、財産分与が予定されているなどの事実を考慮すると、婚姻関係が悪化して、夫婦の一方が別居を決意して家を出る際、夫婦の実質的共有財産に属する財産の一部持ち出しても、その持ち出した財産が将来の財産分与として考えられる対象、範囲を著しく逸脱するとか、他方を困惑させる等不当な目的をもって持ち出したなどの特段の事情がない限り、違法性はなく、不法行為とならないものと解するのが相当である」(東京地裁平4.8.26)
婚姻費用の分担〜私立学校の学費はどうなるの?
少子化傾向にある昨今、子供を私立学校に通わせているご家庭も多いかと思います。
そんな中、やむを得ず別居を選択しなくてはならなくなった場合、私立学校の学費についてはどのように考えればよいのでしょうか。
婚姻費用については、養育費と同様に「婚姻費用算定表」を参考にすることが多いかと思います。
婚姻費用算定表はこちらを参考に。⇒婚姻費用算定表
この婚姻費用算定表については、公立学校の学校教育費が加味されていますが、お子様を私立学校に通わせている場合、私立学校の学費は当然この婚姻費用で賄えるものではありません。
私立学校に通わせている場合の学校教育費と公立学校の場合の費用の差額の負担について以下参考になる裁判例がありますのでご紹介します。
平成26年8月27日大阪高等裁判所
婚姻費用分担審判に対する抗告事件(事件番号 平成26年(ラ)第595号)
この決定では、まず、
私立学校の実際の授業料から、婚姻費用算定表(標準算定方式)で考慮されている公立学校の学校教育費(標準的教育関連費)を控除した額を算出し、これを「超過教育関連費」としています。
そして、この超過教育関連費について
「超過教育関係費は、抗告人及び相手方がその生活費の中から捻出すべきものである。
そして、標準的算定方式による婚姻費用分担額が支払われる場合には双方が生活費の原資と為し得る金額が同額になることに照らして、上記超過額を抗告人と相手方が2分の1ずつ負担するのが相当である」
としています。
つまり、算定表に基づいて一方から他方に対し婚姻費用が支払われる場合、双方の生活費が同レベルになるから、超過教育関連費については半分ずつ負担するのが公平だと判断しているのです。
また、この決定では、超過教育関連費の算定にあたって控除する標準的教育関係費について
「婚姻費用算定表では、公立高校の子がいる世帯の年間平均収入864万4154円に対する公立高校の学校教育費相当額33万3855円が考慮されているが(判タ1111号286頁)、世帯の年収が違えば、学校教育費相当額も変わるとし、当該世帯の年間収入は1411万円であるところ、この場合には54万5000円である」
とし、当事者の収入に応じて標準的教育関係費を計算すべきとしました。
出典 家庭の法と裁判3
婚姻費用の負担額は基本的に当事者間の話し合いで自由に決定することができますが、話し合いの際に参考になるのが婚姻費用算定表であり、上記裁判例です。
別居合意書(婚姻費用分担契約)でお困りの際は一度ご相談くださればと思います。
別居の合意は無効か〜夫婦の同居義務
昨晩のクイズ番組でのこと
「夫婦は同居しなければならないと法律で決められている」
これは正解か間違いか?
結論を言うとこれは正解。
民法は752条で、
「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」
と定めています。
ただ、この規定に罰則はありませんから
仮に別居婚をしたからといって、罰せられるようなことはありません。
また、仕事の都合上単身赴任を強いられている夫婦も多いはず、
このような正当な事情があれば問題ありません。
このように日本の民法は別居制度を採用していません。
また、752条は強行法規※と解されています。
※強行法規というのは、
法令の規定のうちで、それに反する当事者間の合意の 如何を問わずに適用される規定をいいます。
そう考えると、夫婦の別居の合意は無効、
ひいては、当事務所でも作成をさせていただいている別居合意書も無効なのではないかと考えられます。
たしかに、この民法の規定が強行法規であるなら、別居の合意は無効となるでしょう。
実際、以前は別居の合意は無効であるとの見解が有力で、
現在でも、公証人の中には別居合意書や別居を前提とした婚姻費用分担の契約書は作成できないというお考えの方もいらっしゃるようです。
しかし、夫婦関係が危機に瀕しているような場合、別居の合意は夫婦双方の感情的軋轢の冷却化を図り、夫婦間における今後のあり方を検討する熟慮期間を与えることができ、有益でしょう。
また、既に別居している夫婦については、その婚姻費用(生活費)の分担を促すことになるという実情に鑑みて、昨今では少なくとも一時的な別居の合意は有効であるとする説が有力です。
家庭裁判所でも、夫婦関係調整の方法として別居が活用されてきているようです。
したがって、「当分の間別居する」という合意は有効であると考えられます。
別居合意書はこちらを参考に。⇒別居合意書
別居中の子どもと面会交流できるか
妻が子どもを連れて家を出ていってしまい、それから子どもと会っていません。
妻とは離婚することについては合意ができていますが、子どもの親権、財産分与等でしばらく揉めそうです。
離婚が成立するまでの間、このまま子どもとは会えないのでしょうか?
という父親側からのご相談があります。
某タレントさんの離婚問題でも同じようなことがことがあったかと思います。
別居を強いられた親の一方は子どもと面会交流できないのでしょうか?
「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父または母と子の面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他子の監護について必要な事項は、その協議で定める。」
(民法766条)
民法には上記条文があり、協議離婚後の面会交流については定めていますが、別居中の面会交流について明文での規定を設けていません。
しかしながら、子どもと別居中であっても、その子に対する共同親権を持っている状態に変わりありませんから、親権者である以上離婚後にもまして子どもと面会する必要性があるといえるでしょう。
別居中の親にDV等の問題があって、子どもと面会することが子どもの福祉や利益を害するような事情がない限り、面会交流することは認められるでしょう。
この別居中の面会交流については、基本当事者間の協議で定めることになります。
別居合意書を作成する際にも、必要に応じて面会交流についての条項を設けることになります。
相手親との協議で埒があかないときは、家庭裁判所の審判によって、子どもとの面会交流が認められることになります。
女性行政書士が親切丁寧な対応をさせていただきます。
東京 神奈川(横浜) 千葉 埼玉 を中心に別居合意書を作成させていたただきます。
公正証書の作成もお手伝いしております。
夫婦間の契約は取り消せる?
よく、別居合意書も含め、夫婦間契約は直ぐに取り消せるのではないかというご質問があります。
民法には以下のような条文があります。
(民法754条)
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。
たしかに、この条文によると、別居合意書も含め夫婦間契約書を作成しても、すぐ取り消されてしまい、あまり意味がないようにも思えます。
しかし、この条文の趣旨は、
夫婦間の契約は、一方の威力や溺愛の結果、自由な意思を欠くことが多いこと、また、夫婦間契約の履行は当事者の愛情により任意になされるべきであって、法的拘束力をもたせ、訴訟の対象にすることは好ましくない、という点にあります。
この趣旨が妥当するためには、夫婦の関係が愛情をもとに継続されている必要があり、単に形式的に続いている場合のみならず、実質的にも継続していなければなりません。
この点について判断を示した判例があります。
| 最高裁判所判例 昭和33年3月6日 |
| 夫婦関係が破綻に瀕している場合になされた夫婦間の贈与は、これを取り消すことができない。 |
判例時報143号
| 最高裁判例 昭和42年2月2日 |
| 民法754条にいう「婚姻中」とは、単に形式的に婚姻が継続していることではなく、形式的にも、実質的にもそれが継続していることをいうものと解すべきであるから、婚姻が実質的に破綻している場合には、それが形式的に継続しているとしても、同条の規定により、夫婦間の契約を取り消すことは許されないものと解するのが相当である。 |
判例時報477号
つまり、この上記二つの判決に従えば、実質的に破綻している場合に結んだ契約は取り消すことができず、
また、契約を結ぶ時に夫婦が円満でも、取り消す時点で夫婦の関係が実質的に破綻している場合には
もはや取り消せなくなります。
婚姻関係が破綻していると、実質的にみて継続していると言い難いということでしょう。
別居合意書などは、別居をするぐらいですから夫婦の関係は破綻に瀕しているといえるでしょう。
となると別居合意書は取り消せない可能性が高いでしょう。
また、浮気の際に締結するような夫婦間契約書についても、浮気の時点で夫婦関係が拗れてしまっているときに契約した場合、また、最初の浮気ではそこまで拗れなかったけど、次の浮気で夫婦関係が拗れてしまった場合、契約当事者は一方的な意思でこの契約を取り消すことが出来なくなる可能性があるのです。
上記から、別居合意書や夫婦間契約書は、必ずしも取り消されるわけではありません。
夫婦間契約書をご検討の方は是非一度ご相談ください。
女性行政書士が親切丁寧な対応をさせていただきます。
東京 神奈川(横浜) 千葉 埼玉 を中心に夫婦間合意契約書 別居合意書を作成させていたただきます。
公正証書の作成もお手伝いしております。
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日
<離婚相談・遺言・相続>
神奈川県横浜市の「行政書士藤縄純子事務所」では、担当の女性行政書士が東京都内、神奈川県を中心に、離婚相談や遺言・相続のお手伝いをしております。
離婚協議書、婚前契約書、事実婚契約書、夫婦間契約書の作成を代行しております。また、相続のご相談や、遺産分割協議書・遺言書などの公正証書作成のお手伝いも承っております。
親切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問合せください。
| 対応エリア | 東京23区:世田谷区・杉並区・大田区・目黒区・品川区・新宿区・渋谷区等。その他:調布市・狛江市・三鷹市・府中市・町田市、京王線・小田急線沿線や横浜市等が中心ですが、 書面の作成のみでしたら全国対応です。 |
|---|
お気軽にお問合せください
お役立ち情報
不倫・不貞
男女問題
夫婦関係
事実婚・内縁関係
相続・遺言
その他のサービス
事務所紹介
離婚と税金
<業務エリア>東京23区:世田谷区・杉並区・大田区・目黒区・品川区・新宿区・渋谷区等
その他:調布市・狛江市・三鷹市・府中市・町田市、京王線・小田急線沿線や横浜市等が中心ですが、
書面の作成のみでしたら全国対応です。