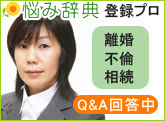〒223‐0061 神奈川県横浜市港北区日吉1丁目7番43号
営業時間 | 9:00~18:00 |
|---|
定休日 | 土日祝祭日 |
|---|
1.親権
日本では、離婚後は単独親権となっていますので(共同親権の選択も可能となる法改正有)、離婚をする際は、どちらが子の親権者となるか決めなくてはなりません。
通常、子供の親権という時は、大きく二つの権限を含みます。
●身上監護権…子供のしつけ、教育をはじめとする子供の身の回りの世話をすること。
●財産管理権…子供の財産を管理し、財産上の法律行為について子を代理すること。
結婚している間は父母が共同で親権を行使します(民法第818条3項)。
しかし夫婦が離婚する場合、どちらか一方を親権者として決めなくてはならず(民法第819条1項)、離婚届けに親権者を記載しなければ、離婚届は受理されませんし、裁判による離婚の時は家庭裁判所が父母の一方を親権者と定めなければならないことになっています。
どちらが親権者になるかの判断基準
●経済的事情
●居住・教育環境
●親族・友人の援助環境
●子供の意思
子供が15歳以上であれば、子供の意思が尊重されますし、15歳以下であっても子供の意思が尊重される傾向にあります。
特に子供が幼ない場合は、特段の事情がない限り母親が優先される傾向にあります。
やはり分娩の事実は大きいですし、幼い子供にとって母親の存在はとても重要なものだからです。
2.監護権
親権について特に父母の間で争いがなければ、夫婦の一方が親権者になりますが、親権について争いがある場合、親権から身上監護権のみを切り離して、親権者とは別に身上監護権者を定めることができます。父親を親権者、母親を監護権者と別々にしていすることもできるのです。そうすればたとえ母親が親権者とはなれなくても、子供と暮らし、子供を育てることが可能になります。
ちょっとした妥協案です。
但し、権限が父親と母親に分属する場合、不都合なこともあります。
例えば親権者を父親、監護者を母にした場合、母親だけでは各種手当の受給ができないことがあり、父親の協力を仰がなければなりません。
また、交通事故の示談等にも法定代理権を有する親権者の協力が必要となり、離婚後も父親と頻繁なやり取りが必要となると想定されます。
いずれにせよ、子供の福祉、生活を考え、何が子供にとって最適か、夫婦が良く話し合ってきめるべきです。
※共同親権を導入する民法の改正案が、2024年5月17日の参院本会議で可決・成立しました。公布から2年後
の2026年までに施行されるとのことになっています。
詳細は離婚Q&Aの共同親権に関する記事を参照⇒離婚Q&A
共同親権とは、未成年の子どもについて、父母双方が共同して親権を行使する制度です。
女性行政書士が親切丁寧な対応をさせていただきます。
東京 神奈川(横浜) 千葉 埼玉 を中心に離婚協議書の作成をさせていただきます。
公正証書の作成もお手伝いさせていただきます。
1.養育費とは?
養育費というのは、未成熟な子供が、経済的に自立した社会人として成長するまでに要する全ての費用、つ まり、子の通常の衣食住の費用、教育費、医療費、適度の交際費等が含まれます。
養育費を受け取ることは子供の権利であると考えられています。
と同時に、養育費を支払うことは子供に対する親の義務であり、子供と一緒に生活しない親でも支払う必要があるのです。
親の子に対する扶養義務は、「生活保持義務」といって、親は自分の生活を削ってでも、子どもに同等の生活をさせなければなりません。
収入が低い、借金があるという理由で免れられるものではないのです。
しかし、離婚して子供を引き取ったのに養育費をもらっていない母子家庭が相当多く、受け取っている家庭は全体の2割程度というのが現状です。
2.養育費の額
親はその経済力に応じての養育費を支払う必要があります。
養育費の額は基本的には、父母双方の資産、収入、生活状況等の事情を考慮して、夫婦の協議で決めます。
どのような基準で決めたらいいのかわからない場合、参考になるのが「養育費算定表」です。
これは東京・大阪の裁判官らにより構成される東京・大阪養育費等研究会が提案したものですが、家庭裁判所による調停等ではこの表を参考に決定されるようです。
この表は子供の数、年齢、親の収入別の養育費の参考額がわかるようになっています。
一般の家庭においては、子供一人につき3万円前後、子供二人で4〜6万円程度が多いようです。
この「養育費算定表」は、家庭裁判所のHPに掲載されていますので参考になさるとよいでしょう。
当事者間の協議で決まらないときは、やはり調停を申し立てて、調停の場で解決することになります。
3.養育費の支払期間
養育費支払いの始まりの時期については、離婚をして要扶養状態が生じたときということになりますので、「離婚をした月から」、若しくは「離婚した月の翌月から」と定めることが多いでしょうか。
一方養育費支払いの終わりの時期につきましては、子供が社会人として「自立」するまでとされています。
「自立」の解釈は18歳になるまで、20歳になるまで、大学を卒業するまでと様々ですが、夫婦の合意が得られない場合は、やはり調停を申し立てることになります。
調停では、親の資力、学歴といった家庭環境によって判断するようです。
親が大学を出て、そこそこの資力があるのなら、大学卒業まで養育費を支払うのが相当との判断になりやすいといえます。
4.養育費を決める際のポイント
養育費の取り決める際は、
●一括でもらうか毎月分割でもらうか※
●毎月何日にどの口座に振り込むか
●子供が何歳まで支払うか
●子供が私立の学校に進学した時はどうするか
等細かく定めておいた方が後々トラブルにならずにすみます。
皆が円満に別れられるわけではありません。
別れた後話し合いできめるのはのは非常に困難です。
できれば離婚なさる際に離婚協議書などの文書の形にして残しておくべきでしょう。
※養育費は基本毎月払いが原則です。
事情により一括で支払う旨の取り決めをすることもありますが、養育費を早期に使い切ってしまうという問題や 税金の問題等様々な問題がありますので、ご検討の場合は一度専門家にご相談なさることをお勧め致します。
5.養育費支払いの確保
養育費は長い期間にわたって支払われるものです。
初めのうちは順調に支払ってくれるのですが、相手が再婚などして新しい妻、子供が生まれたりするとなかなかスムーズに支払ってはもらえなくなるもの。
このような事態を避けるため、養育費の取り決めをした離婚協議書を公正証書にし、強制執行認諾条項をいれておけば、支払いが滞った時、裁判によることなく相手の財産、給与を差し押さえることができるようになります。
養育費を名目として差し押さえる場合、相手の給与の1/2まで差し押さえることが可能になりました。
また以前は、強制執行は過去の滞納分に限られており、その都度強制執行しなければならず、極めて不便でしたが、平成15年8月民法、民事執行法が改正され、一度の申し立てで将来に亘って差し押さえできるようになりました。
女性行政書士が親切丁寧な対応をさせていただきます。
東京 神奈川(横浜) 千葉 埼玉 を中心に離婚協議書の作成をさせていただきます。
公正証書の作成もお手伝いさせていただきます。
1.面会交流権とは?
離婚して子供と暮らさなくなった父母の一方が、子供と定期的に会い、交流を持つことができる権利のことをいいます。
この権利は子供と離れて暮らす親が、子供と触れ合う権利です。
離婚しても親子は親子なのですから、特別な理由がない限りこれを拒否することはできません。
しかし、面会交流も子供の福祉の観点から制限されることもあります。
例えば、
①親が子供に暴力をふるう可能性がある(DVが原因の離婚など)
②子供が強く拒否している
③養育費を支払う能力があるにもかかわらず、正当な理由なくこれを拒んでいるとき
面会交流権は離婚の際、父母の協議で定めることになりますが、協議がまとまらない場合や相手が応じない場合は家庭裁判所に調停の申し立てをすることができます。
2.面会交流権に関して決める事項
①面会の回数
②面会の場所(泊もありか否か)
③面会の際の連絡方法
④会わないときのメール、電話等の連絡方法
など、できればさらに具体的に決めておいたほうがよいでしょう。
夫婦であったものが他人になるのです。
良好な関係が保てればよいのですが、激しく対立して別れた場合など、コミュニケーションがうまく取れず、トラブルの元になりかねません。
きっちりと離婚協議書という書面の形にして残しておく必要があります。
子供を監護する親が、子供と会わせないなど面会交流権が実現されない場合、これが債務不履行となり損害賠償責任が生じる可能性もあります。
相手が正当な理由もなく子供と面会させない場合、子供の状況も考慮しながら、
①内容証明郵便で面会交流の実現を相手に請求する
②家庭裁判所に調停、審判の申し立てをする
などの方法をとることになります。
養育費、面会交流の取り決めについて
以前は、離婚後の子に係る養育費、面会交流の取り決めについて、民法上特に規定されていませんでした。
しかし、「民法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第61号)により民法第766条が改正され,平成24年4月1日から施行されることとなりました。
改正後の民法第766条では,父母が協議上の離婚をするときに協議で定める「子の監護について必要な事項」の具体例として「父又は母と子との面会及びその他の交流」(面会交流)及び「子の監護に要する費用の分担」(養育費の分担)が明示されるとともに,子の監護について必要な事項を定めるに当たっては子の利益を最も優先して考慮しなければならない旨が明記されました。
民法第766条1項
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子の交流、子の 監護に要する費用の分担その他のの子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
これに伴い法務省は、養育費と面会交流の取り決め方や,その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成しています。
参考にしてみてください。
女性行政書士が親切丁寧な対応をさせていただきます。
東京 神奈川(横浜) 千葉 埼玉 を中心に離婚協議書の作成をさせていただきます。
公正証書の作成もお手伝いさせていただきます。
子どもの氏は、子の出生時に決まり、父母が婚姻中に共同で称していた氏とされます。
父母が離婚しても子どもの氏は当然に変わることはありません。
子どもの親権者となった母親が復氏して旧姓に戻った場合で、子が母の氏を名乗るためには、子の氏の変更をしなければなりません。
また、子どもは離婚により当然に戸籍も変動することはありませんので、従前の戸籍に残ることになります。
上記のような場合には、一定の手続きをとることによって母子の氏と戸籍を同じにすることができます。
まず、家庭裁判所に子の氏の変更について申し立て(民法791条)、その許可を得る必要があります。
管轄は、子の住所地を管轄する家庭裁判所です。
子が15歳未満の場合は、法定代理人(親権者)が代わってこれを行います。
この氏の変更許可を受けた後、市区町村長に対して「子の母の氏を称し母の戸籍に入籍する」旨の入籍届をします。
この手続きを経て晴れて子は母の氏を名乗り、母の戸籍に入れることができるのです。
では、母が旧姓に戻らず、婚姻時の氏を引き続き使用する場合はどうでしょう。
少しわかりづらいのですが、仮に子の親権者となった母親が、旧姓に戻らず、婚氏続称を届け出し、婚姻中に使用していた氏を継続して使用することになったとしても婚氏続称で使用する氏は、婚姻中に使用していた氏とは法律的にみて別のものとなります。
例えば「A木」という女性が「B藤」という男性と結婚し、「B藤」という氏を称することになったとします。
この夫婦の間にできた子も当然「B藤」という氏を名乗ることになります。
仮にこの夫婦が離婚することになり、子の親権者・監護権者は母親になったとします。
子の氏は両親の離婚によって当然に変わることはありませんので「B藤」のままです。
ただ、母親が婚氏続称の届出をし、そのまま「B藤」という氏を称することになっても、この母親の「B藤」と子の「B藤」は法律上異なることになるのです。
ですので、子が母の氏の「B藤」を名乗るためにはやはり子の氏の変更をしなければなりません。
この氏の変更許可を受けた後、市区町村長に対して「子の母の氏を称し母の戸籍に入籍する」旨の入籍届をします。
この手続きを経て晴れて子は母の氏を名乗り、母の戸籍に入れることができるのです。
女性行政書士が親切丁寧な対応をさせていただきます。
東京 神奈川(横浜) 千葉 埼玉 を中心に離婚協議書の作成をさせていただきます。
公正証書の作成もお手伝いさせていただきます。
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日
<離婚相談・遺言・相続>
神奈川県横浜市の「行政書士藤縄純子事務所」では、担当の女性行政書士が東京都内、神奈川県を中心に、離婚相談や遺言・相続のお手伝いをしております。
離婚協議書、婚前契約書、事実婚契約書、夫婦間契約書の作成を代行しております。また、相続のご相談や、遺産分割協議書・遺言書などの公正証書作成のお手伝いも承っております。
親切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問合せください。
| 対応エリア | 東京23区:世田谷区・杉並区・大田区・目黒区・品川区・新宿区・渋谷区等。その他:調布市・狛江市・三鷹市・府中市・町田市、京王線・小田急線沿線や横浜市等が中心ですが、 書面の作成のみでしたら全国対応です。 |
|---|
お気軽にお問合せください
お役立ち情報
不倫・不貞
男女問題
夫婦関係
事実婚・内縁関係
相続・遺言
その他のサービス
事務所紹介
離婚と税金
<業務エリア>東京23区:世田谷区・杉並区・大田区・目黒区・品川区・新宿区・渋谷区等
その他:調布市・狛江市・三鷹市・府中市・町田市、京王線・小田急線沿線や横浜市等が中心ですが、
書面の作成のみでしたら全国対応です。