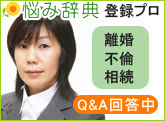〒223‐0061 神奈川県横浜市港北区日吉1丁目7番43号
営業時間 | 9:00~18:00 |
|---|
定休日 | 土日祝祭日 |
|---|
面会交流を間接強制①
離婚時に決めた面会交流がなかなか実現されないことで困っている方も多くいらっしゃるかと思います。
面会交流を実現する方法の一つとして考えられるのは、間接強制です。
間接強制というのは、債務者(義務者)に対して、金銭の支払を命じるなど一定の不利益を課すことにより心理的に圧迫し、義務の履行を強制する方法です。
判例で、面会交流の間接強制が認められる場合とその具体的条項の内容が明らかになっています。
最高裁平成25年3月28日決定(平成24年(許)第48号)間接強制に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判において、面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合は、上記審判に基づき監護親に対し間接強制決定をすることができる、とした上で、次の①、②のとおり定められているなど判示の事情の下では、監護親がすべき給付の特定に欠けるところはないといえ、上記審判に基づき監護親に対し間接強制決定をすることができるとしています。
①面会交流の日程等は、月1回、毎月第2土曜日の午前10時から午後4時までとし、場所は、子の福祉を考慮して非監護親の自宅以外の非監護親が定めた場所とする。
②子の受渡場所は、監護親の自宅以外の場所とし、当事者間で協議して定めるが、協議が調わないときは、所定の駅改札口付近とし、監護親は、面会交流開始時に、受渡場所において子を非監護親に引き渡し、子を引き渡す場面のほかは、面会交流に立ち会わず、非監護親は、面会交流終了時に、受渡場所において子を監護親に引き渡す。
離婚協議書の面会交流条項作成で参考になりそうですね。
女性行政書士が親切丁寧な対応をさせていただきます。
東京 神奈川(横浜) 千葉 埼玉 を中心に離婚協議書の作成をさせていただきます。
公正証書の作成もお手伝いさせていただきます。
面会交流を間接強制②
続いて、間接強制が認められなかったケースです。
最高裁平成25年3月28日決定(平成24年(許)第47号)
間接強制申立ての却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
非監護親と子が面会交流をすることを定める調停調書に基づき間接強制決定をすることができないとされた事例
非監護親と監護親との間において非監護親と子が面会交流をすることを定める調停が成立した場合において、調停調書に次の①、②のとおり定められているなど判示の事情の下では、監護親がすべき給付が十分に特定されているとはいえず、上記調停調書に基づき監護親に対し間接強制決定をすることはできない。
① 面会交流は,2箇月に1回程度,原則として第3土曜日の翌日に、半日程度(原則として午前11時から午後5時まで)とするが、最初は1時間程度から始めることとし、子の様子を見ながら徐々に時間を延ばすこととする。
② 監護親は、上記(1)の面会交流の開始時に所定の喫茶店の前で子を非監護親に会わせ、非監護親は終了時間に同場所において子を監護親に引き渡すことを当面の原則とするが、面会交流の具体的な日時、場所、方法等は、子の福祉に慎重に配慮して、監護親と非監護親間で協議して定める。
こちらの条項については、面会交流の頻度について、「2か月に1回程度」とし、また、
面会交流時間の長さについても、「半日程度(原則として午前11時から午後5時まで)」としつつも、「最初は1時間程度から始めることとし、長男の様子を見ながら徐々に時間を延ばす…」とするなど、幅のある記載になっています。
また、「面接交渉の具体的な日時、場所、方法等は、子の福祉に慎重に配慮して、相手方
との間で協議して定める」としていることに照らすと、調停調書では面会交流の大枠を定め、
具体的な内容は当事者間の協議で定めることを予定しているといえることから、相手方が
すべき給付が十分特定されていないと判断されました。
こちらも、離婚協議書の面会交流条項を作成する際の参考になりそうですね。
医学部進学のための扶養料
子の大学の学費については、大学進学の経緯や親の学歴、収入等を考慮して請求が認められるか否かを判断することになります。
では、医学部進学の学費(かなり高額になります)についてはどうでしょう。
参考になる裁判例をご紹介します。
【事案の概要】
この事案は、私立大学医学部に通う申立人(長男、成人)が、相手方(父)に対し、現在の養育費では学費等に不足が生じているとして扶養料の支払を求めたものです。
医師である父と薬剤師の資格を持つ母との離婚(平成24年に調停離婚)に際し、申立人ら子に対しかなり高額の養育費(子一人につき月額25万円と500万円の一括金)が定められたが、その後申立人が二浪して私立の医学部に進学したことから、医学部6年間の学資(大学学納金やPTA会費の合計額は6年間で約3200万円)の分担が問題になりました。
相手方は離婚後再婚し、申立人らとの面会を拒否していた。
相手方は開業医(平成28年の事業所得4851万円)
母は薬剤師
【裁判所の判断】
申立人(長男)の私立大学医学部への進学に係る追加費用の負担について
相手方(父)は、母への離婚申入れ当時から、申立人が医学部を含めて大学を卒業するまで申立人を扶養する義務を引き受ける旨伝えていた。
離婚時の調停条項でも、養育費支払義務の終期を申立人の医学部を含む大学卒業までとすることを了承していた。
また、相手方は、離婚時に、子らの養育費(1人当たり月額25万円)の支払とは別に、私立大学の医学部に進学する場合を想定した協議条項(医学部進学の場合の協議事項)に合意していた。
上記のような離婚時の合意に至った経緯、医学部に進学する場合を想定した協議条項の内容、父母ともに医師の一家に育ち、父は医師として高額の収入を得ていることからすると、離婚当時、申立人が私立大学医学部への進学を希望すればその希望に沿いたいとし、その場合、養育費のみでは学費等を賄えない事態が生じることを想定し、申立人からの申し出により、一定の追加費用を負担する意向を有していたと認めるのが相当である。
として相手方の追加負担額を6年間で880円程度と認定した。
大阪高等裁判所 平成29年12月15日
家庭の法と裁判 17号
お子様の養育費に関しては、上記のような医学部への進学の場合のみならず、大学院への進学や海外留学等の場合も想定されるかと思います。
この裁判例を見ていると、当事者の意思や両親の属性に加え、離婚時の調停条項(協議離婚の場合は離婚協議書)に記載される合意内容が重視されていることが分かります。
つくづく離婚協議書において詳細に取り決めておくことの重要性を実感します。
女性行政書士が親切丁寧な対応をさせていただきます。
東京 神奈川(横浜) 千葉 埼玉 を中心に離婚協議書の作成をさせていただきます。
公正証書の作成もお手伝いさせていただきます。
養育費は大学卒業までもらえるのか
親は、独立して生活を営むことができない「未成熟子」に対し扶養義務を負うとされています。この「未成熟子」というは一般に成年に達しない子とされています。
上記から考えると養育費は原則20歳までということになります。(民法改正により2022年4月から成人年齢が18歳に引き下げられました)。
ただ、子が大学等に進学しており、成人していても独立した生計を営んでいないような場合には、親の扶養義務が認められる場合があります。
以下、参考になる裁判例をご紹介します。
【事案の概要】
妻から夫に対して離婚を求めるとともに、3人の子の親権、養育費、財産分与等を求めた事案。
以下のように述べて養育費支払義務の終期を22歳までとしました。
「養育費支払義務は、一般には子が成人に達した段階で消滅するのが原則と考えられる。しかし、その一方で、4年生大学への進学率が相当高い割合に達している現状において、子が大学へ進学する場合、学費や生活費に不足を生じることはやむを得ないことと言うべきである。本件においては、非監護親は、監護親の収入を十分に承知したうえで、子が大学を卒業することを強く望んでいる旨を明確に述べているから、子の大学進学に関する費用を自らが負担する旨の認識を示したものと判断することができる。
また、もし、将来子が大学に進学しなかった場合には、そのことが明らかになった段階で、家庭裁判所に養育費減額等の申し立て等を行うことにより不合理な結論を避けることは十分に可能である。よって、本件においては、子供らが成年に達した後においても、4年制大学の卒業が予定される満22歳時までは、養育費支払義務が継続されるべき格別の事情が存在するものと認められ、夫が支払うべき養育費の終期は子供らの満22歳に達するまでと定めるのが相当である。」と判断しました。
東京地方裁判所平成17年4月15日
上記は、支払義務者(父親)も子の大学進学を望んでいる場合ですので全ての事案に当てはまるわけではありません。
では、支払義務者が大学進学に同意していなかった場合はどうでしょう。
以下、参考になる裁判例をご紹介します。
【事案の概要】
成年に達した子が自ら親に対し大学在学中の扶養料を求めた事案。
「抗告人(子)の大学進学は相手方である父の同意を得たものではなく、一般に成年に達した子の大学教育の費用を親が負担すべきであるとまでは言えないが、4年生大学への進学率が高まってきており、相手方の学歴や抗告人の学業成績からすれば、抗告人の4年生大学進学は予想されていたこと、抗告人及び同居親である母の収入だけでは抗告人が大学で学業を続けながら生計を維持することは困難であること、相手方は今後とも一定程度の収入を得ることが見込まれること、相手方が話し合いによるものであれば一定額の支払に応じると述べているなどの一切の事情を考慮すれば、相手方に対し、抗告人の学校関係費用、生活費等の不足額の一部を、原告が大学を卒業すると見込まれる月まで、扶養料として支払うよう命じるのが相当である。」と判断しています。
東京高等裁判所平成22年7月30日
(家庭裁判月報)
ただ、上記裁判例は、抗告人(子)が大学卒業まで毎月15万円の支払いを求めたのに対し毎月3万円の支払いを命じたに止まり、これは父親が支払に応じると述べていた額でした。
養育費をいつまで支払うかについては、当事者間で合意さえできれば基本当事者の自由であり、大学卒業まででも、大学院進学の場合は大学院卒業までと取り決めることもできます。
離婚協議書の作成をご検討であれば是非ご相談ください。
女性行政書士が親切丁寧な対応をさせていただきます。
東京 神奈川(横浜) 千葉 埼玉 を中心に離婚協議書の作成をさせていただきます。
公正証書の作成もお手伝いさせていただきます。
配偶者の不貞相手に離婚慰謝料は請求可能か
配偶者の不貞行為が原因で夫婦が離婚した場合,不貞の相手に,離婚したことに伴う精神的苦痛に対する慰謝料を請求できるかが争われていた事案について、平成31年2月19日、最高裁判所の判決が出ました。
【事案の概要】
原告の男性が、被告男性に対し、自身の妻であったAと被告男性が不貞行為に及び、これにより離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったと主張して、不法行為に基づき、慰謝料等の支払いを求めたもの
一般に、配偶者の不貞の相手に対しては,離婚が成立したか否かに拘わらず不貞行為に対する慰謝料を請求できるとされています。そしてこの場合、不法行為に基づく損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から3年間で時効消滅すると定められていますので、不貞行為や相手方のことを知ってから3年経過すると、損害賠償請求することが基本的にできなくなってしまいます。
今回の事案でも、原告男性が元妻Aと不貞相手の男性の不貞行為を知ったときから3年以上経過していたため,不貞相手の男性から、損害賠償請求権が時効消滅しているとの反論がなされていました。
原告の男性の請求に対し下級審は、
被告男性とAとの不貞行為により原告とAとの婚姻関係が破綻して離婚するに至ったものであるから,被告男性は,両者を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負い,原告は,被告男性に対し,離婚に伴う慰謝料を請求することができるとして200万円の支払いを命じていました。
この裁判例では、不貞行為に対する慰謝料ではなく、離婚に伴う慰謝料として認める形になっています。この事案の場合、離婚から3年以内の提訴だったので、時効には掛かっていないという判断です。
これに対し最高裁判所は以下のとおり示して原告男性の請求を棄却しています。
夫婦の一方は,他方に対し,その有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことを理由としてその損害の賠償を求めることができるが、離婚による婚姻の解消は,本
来,当該夫婦の間で決められるべき事柄である。
夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても,当該夫婦の他方に対し、直ちに,当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。
第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは,当該第三者が,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られる。夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対し、上記特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することはできない。
そして本件の被告男性については、特段の事情があったことは伺われない。
この事案の場合、もし被告男性が積極的に家庭を壊そうとしていたような場合であれば違った結論が出ていたのかもしれないですね。
最高裁判所判決参照
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/422/088422_hanrei.pdf
有責配偶者からの離婚請求は認められるか?①
、有責配偶者とは、離婚原因を作ったことに責任のある配偶者のことをいいます。
例えば、不貞行為やDV等暴力を行った配偶者が典型でしょうか。
正確な定義をしますと、「有責配偶者」とは、民法770条1項各号所定の事由について「専ら又は主として責任のある一方の当事者」だとされています(最高裁昭和62年9月2日大法廷判決・民集41巻6号1423頁参照)。
※第770条1項
1 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
当事務所でも配偶者が浮気して家を出てしまい、離婚を求められているというご相談をいただくことがございます。
有責配偶者からの離婚請求は認められるのでしょうか。
(民法770条1項5号を主張して離婚請求できるか)
結論から申し上げて、有責配偶者からの離婚請求すべてが否定されるわけはありませんが、原則認められないということになります。
自ら離婚の原因を作っておきながら、責任のない相手方に離婚を求めることは人道上許されないという趣旨です。
ただし、例外的に以下の要件を満たした場合に認められています。
①長期間の別居(婚姻関係が破綻している)
②未成熟な子どもがいないこと
③離婚により、相手配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれないこと
判例をご紹介します。
最高裁判所 昭和61(オ)260 昭和62年9月2日 民集 第41巻6号1423頁
【事案の概要】
昭和12年に婚姻した夫婦 子が生まれなかったため女児二人と養子縁組。
昭和24年頃、夫の不貞行為を契機として家庭が不和になる。その後夫は不貞相手と同棲するようになり、以後36年間別居が継続。この間妻は夫から生活費を一切受け取っていない。
昭和26年頃、夫が東京地裁に離婚を求める訴えを提起。
婚姻関係が破綻するに至ったのは夫が不貞行為に及び、妻を悪意で遺棄して不貞相手と同棲を継続していることに原因があるから、有責配偶者からの離婚請求に該当するとして棄却される。
昭和58年12月頃、夫が東京家庭裁判所に離婚を求める調停を申し立てたが、不調に終わったため本訴えを提起。
裁判所の判断
1 有責配偶者からされた離婚請求であっても、夫婦がその年齢及び同居期間との対比において相当 の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできない。
2 夫は有責配偶者というべきであるが、夫と妻の別居期間は36年に及び、同居期間や双方の年齢と対比するまでもなく相当長期間であり、しかも、両者の間には未成熟の子がいないのであるから、精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がない限り、これを認容すべきものである。
当初は有責配偶者からの離婚請求ということで離婚は認められませんでしたが、36年もの長きに亘る別居期間を経てやっと認容すべきとの判断が出されました。
この判決以降、離婚請求の可否については、別居期間、未成熟子の存在、苛酷状態等の事情を総合的に考慮して、有責配偶者の離婚請求が信義則に照らし許されるか否かを判断する方法が多くとられています。
最高裁判所判決参照
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55213
有責配偶者からの離婚請求は認められるか?②
その後の判例の流れをご紹介します。
8年の別居期間で認めなかったものと、認めたものがあります。
〇認めなかった事案
最高裁判所 昭和62(オ)839 平元・3・28判決
【事案の概要】
昭和30年に婚姻した夫婦。二男二女を儲ける。
昭和51年頃から夫が職場の部下と不貞関係になり、昭和56年頃から夫はその不貞相手と同棲状態になった。
その後夫が離婚を求める訴えを提起。
事実審の口頭弁論終結時、夫69歳、妻57歳。
未成熟の子なし。別居期間8年。
裁判所の判断
1 有責配偶者からされた離婚請求であっても、夫婦がその年齢及び同居期間との対比において相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできない。
2 夫は有責配偶者というべきであるが、事実審の口頭弁論終結時、夫60歳、妻57歳であり、婚姻以来26年余同居して二男二女を儲けた後夫が他の女性と同棲するため妻と別居して8年余になるなど判示の事情のあるときは、夫婦の別居期間が双方の年齢及び同居期間と対比して相当の長期間に及ぶということができず、右離婚請求を認容することができない。
最高裁判所判決参照
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62373
最高裁判所 平成1(オ)1039 平成2年11月8日 判決 集民 第161号203頁
〇認めた事案
【事案の概要】
昭和33年5月に婚姻した夫婦。二男を儲ける。
昭和56年頃夫が家を出て別居し、それ以降別居を継続。
夫は別居の前から妻以外の女性と情交関係にあり、別居後同女性と同棲するようになる。(間もなく同女性とは別れる。)
事実審口頭弁論終結時点で夫52歳、妻55歳、長男29歳、二男24歳。別居期間8年。
別居期間中夫は妻子の生活費を負担。夫から妻へ財産関係の清算につき具体的で相応の誠意があると認められる提案がされている。
裁判所の判断
1 別居期間が相当の長期間に及んだかどうかを判断するに当たっては、別居期間と当事者の年齢及び同居期間とを数量的に対比するのみでは足りず、時の経過が当事者双方の諸事情に与える影響も考慮に入れるべきものであると解するのが相当である。
2 有責配偶者である夫からされた離婚請求において、夫が別居後の妻子の生活費を負担し、離婚請求について誠意があると認められる財産関係の清算の提案をしているなど判示の事情のあるときは、約八年の別居期間であっても、他に格別の事情のない限り、両当事者の年齢及び同居期間との対比において別居期間が相当の長期間に及んだと解すべきである。
最高裁判所判決参照
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=76103
有責配偶者からの離婚請求は認められるか?③
その後の事例
最高裁判所ではありませんが、高等裁判所の判断をご紹介します。
東京高等裁判所 平成30年(ネ)3466 平30・12・5判決
【事案の概要】
平成5年に婚姻した夫婦。二女を儲ける。
平成23年6月から夫は、妻、子、要介護の実父を都内のマンションに残し単身赴任。
その直後の同年7月、夫、妻へ離婚話を切り出す。
以後、実父の世話を妻に任せたまま家族との一切の連絡を絶ち、別居期間は7年になる。
平成24年夫は第1次離婚訴訟を提起する。
平成25年敗訴が確定。
平成28年夫の実父死亡
平成29年夫は第2次離婚調停を申し立てるが不調に終わる。
その後夫第2次離婚訴訟を提起。
夫は会社員、妻は専業主婦、子は長女が成人に達し、次女は高校生。
裁判所の判断
第1審は、別居期間が7年近くに及び、夫の離婚意思が強固であり、婚姻を継続し難い重大な事由があると判断した。
また、妻が夫に無断で夫の実父と養子縁組をしたり、金銭の贈与を受けたり、夫の実父の生命保険金の受取人を娘らに変更したことで、夫の離婚意思が強固になってもやむを得ないと判断しました。
これに対し第2審の東京高等裁判所は、婚姻関係維持の努力や別居中の相手方配偶者及び同居家族(娘、実父)への配慮が皆無であるという事実関係においては、別居期間が7年継続し、夫の離婚意思が強固であっても、婚姻を継続し難い重大な事由があるとは言えないと判断しました。
また、仮に婚姻を継続し難い重大な事由があるとしても、離婚請求が信義則に照らして認容されるかどうかを検討するべきであり、その場合の考慮要件として、①離婚原因発生についての寄与の有無、態様、程度、②相手方配偶者の婚姻継続意思等、③離婚を認めた場合の相手方配偶者の精神的、経済的、社会的状態及び子の福祉、④別居後に形成された生活関係、⑤時の経過がこれらに与える影響、を挙げました。
その上で、本件では、離婚原因の発生原因は専ら夫にあり、妻は強い婚姻継続の意思を持ち、離婚を認めることにより妻と娘等が経済的精神的苦境に陥り、時の経過がこれらの状況を軽減・解消するような状況はみられないとして本件離婚請求は信義則に反して許されないと判断しました。
判例タイムズ1461号P126
女性行政書士が親切丁寧な対応をさせていただきます。
東京 神奈川(横浜) 千葉 埼玉 を中心に離婚協議書の作成をさせていただきます。
公正証書の作成もお手伝いさせていただきます。
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日
<離婚相談・遺言・相続>
神奈川県横浜市の「行政書士藤縄純子事務所」では、担当の女性行政書士が東京都内、神奈川県を中心に、離婚相談や遺言・相続のお手伝いをしております。
離婚協議書、婚前契約書、事実婚契約書、夫婦間契約書の作成を代行しております。また、相続のご相談や、遺産分割協議書・遺言書などの公正証書作成のお手伝いも承っております。
親切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問合せください。
| 対応エリア | 東京23区:世田谷区・杉並区・大田区・目黒区・品川区・新宿区・渋谷区等。その他:調布市・狛江市・三鷹市・府中市・町田市、京王線・小田急線沿線や横浜市等が中心ですが、 書面の作成のみでしたら全国対応です。 |
|---|
お気軽にお問合せください
お役立ち情報
不倫・不貞
男女問題
夫婦関係
事実婚・内縁関係
相続・遺言
その他のサービス
事務所紹介
離婚と税金
<業務エリア>東京23区:世田谷区・杉並区・大田区・目黒区・品川区・新宿区・渋谷区等
その他:調布市・狛江市・三鷹市・府中市・町田市、京王線・小田急線沿線や横浜市等が中心ですが、
書面の作成のみでしたら全国対応です。