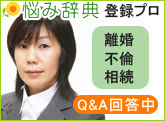〒223‐0061 神奈川県横浜市港北区日吉1丁目7番43号
営業時間 | 9:00~18:00 |
|---|
定休日 | 土日祝祭日 |
|---|
夫婦別産制とは
財産分与を考えるにあたっては、先ず、日本における夫婦の財産制について知っておく必要があります。
日本の民法は夫婦別産制をとっています(民法762条1項)。
これは、夫婦は平等という原則から、夫も妻も等しく自分の特有財産を管理・収益する権利を取得し、夫婦の財産の峻別を図る制度です。
※762条
1項 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の 一方が単 独で有する財産をいう。) とする。
2項 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
即ち、結婚前から各人が持っている預金や不動産等の財産や、結婚後であっても相続や贈与など自己の名前で得た財産は、各人の特有財産(単独所有)であり、各人が処分、収益する権利を取得する。結婚したからと言って当然に夫婦の共有になるわけではないということです。
夫婦の財産は①特有財産、②共有財産、③実質的共有財産の3つに分けて考えることになります。
① 特有財産
結婚前から持っていた財産や相続等で得た財産であり、その取得に際し他方の協力がなかった名実ともに各
人の財産です。
② 共有財産
夫婦の共同生活の中で購入した家具、家電を含む家財道具等、取得に際し夫婦が協力した名実共に共有の財産です。
③ 実質的共有財産
名義は一方にあるが、取得に際し他方の協力があったとして実質的には夫婦の共有となる財産です。例えば、各人が婚姻中に労働の対価として得る給与、賞与等は、762条1項から表面上は①の特有財産ということになりますが、これらは他方の協力があって得られるものだから実質的共有ということになります。給与や賞与を元手として購入する不動産もここに分類されることになるかと思います。
財産分与の対象になるのは婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産であることから、原則として②③の財産が対象ということになります。
財産分与
財産分与とは、離婚する際に夫婦の一方ら他方へ財産を分け与えることです。
財産分与は以下3つの性格を併せ持つと言われています。
①清算的財産分与 夫婦の協力して築き上げた財産を、離婚にあたり清算するという性格
②扶養的財産分与 離婚後、生活に困る配偶者を扶養するという性格
③慰謝料的財産分与 離婚されたこと自体を原因として生じる精神的損害を慰謝するという性格
離婚の際問題になるのは主に①の清算的財産分与です。
この清算的財産分与の場合、分与の対象となる財産は原則として、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産ということになります。
前の記事「夫婦別産制とは」の中で記載した②③の財産が分与対象となります。
結婚前から持っていた財産や、婚姻中であっても相続や贈与等自己の名義で得た財産①は対象にはなりません。
実務においては、財産分与の割合は特段の事情のない限り2分の1(2分の1ルール)とすることが多いようです。ただし、当事者間で合意があれば、どのような割合で清算しても構いません。
その他財産分与には、離婚後の扶養としての性格を持つ扶養的財産分与、離婚に伴う慰謝料としての性格を持つ慰謝料的財産分与がありますが、これらの財産分与をするかしないかは任意ということになり、当事者間の協議で決めることになります。
財産分与の対象
財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産です。
具体的には、不動産、現金、預貯金、株式、自動車、ゴルフ会員権、退職金(近い将来受領できる可能性が高いものは対象になります)等でしょうか。
貯蓄性のあるものであれば、保険なども分与の対象になり得ます。
夫婦の一方が婚姻前から有していた財産や、相続等単独名義で取得した財産については、財産分与の対象にはなりません。
夫婦共有名義の財産は原則的に財産分与の対象になります。
また、たとえ単独名義になっていたとしても、夫婦が協力して形成した財産という実質があれば、実質的共有財産として財産分与の対象になります。
例えば、夫がローンを組んで、夫の単独名義になっているご自宅があるとします。
表向きは夫の名義だったとしても、夫が働き、給与を得られるのは妻が家事や育児を担っているから、つまり妻の貢献があってこそのことと思います。
潜在的に妻にも持分があると考えられますので、この場合、この不動産は実質的にはご夫婦の共有財産となり、財産分与の対象になると考えられます。
なお、住宅や自動車等当該財産の取得に際しローンを組んだ場合、一般に、財産の価額からローンの残額を引いたものを現在の価値として財産分与の対象にします。
この清算的財産分与を行う場合は、まず夫婦共有財産のリストを作ることからはじめるとよいでしょう。
夫婦間の話し合いがスムーズになりますし、その後調停等になった場合に役に立ちます。
財産分与の時期
財産分与(清算的財産分与)というのは、財産における夫婦の実質的な共有関係を解消するのですから、基本的に婚姻関係を解消した場合に清算することになります。
因みに、離婚時に財産分与を取り決めなくても、離婚後2年以内であれば財産分与の請求は可能です。
では、分与対象となる財産を確定する基準時はいつになるのでしょうか?
通常は、離婚時に存する財産(婚姻前の財産や相続や贈与で得た財産を除く)が対象になりますので離婚時ということになります。
では、当該夫婦が別居していた場合はいつが基準時となるのでしょうか。
財産分与の趣旨は、婚姻期間中に協力して形成した財産を離婚にあたり清算することにあります。ですので、原則として、その協力関係が終了した時点の財産を対象とすることになります。
別居時にはその協力関係が終了していると考えられますので、原則別居時が基準時となり、別居時に存する財産が対象になります。
別居時以降離婚前に財産を取得しても、本来、それは財産分与の対象にはなりません。
不動産について
仮に夫名義で不動産を購入し、夫名義で住宅ローンを借り入れ、返済していたとしても、住宅ローンの返済には妻の潜在的貢献がありますので、この不動産は財産分与の対象になります。
ただし、別居時以降の住宅ローンの返済に関しては、夫婦の協力関係が終了していますので、この期間の返済分に関しては夫の特有財産として清算割合を検討することになろうかと思います。
もちろん、上記は、原則的な考え方ですので、当事者間で合意が出来れば、どの時点の財産を、どのような割合で清算しても構いません。
後悔しない離婚のために、女性行政書士が親切丁寧な対応をさせていただきます。
東京 神奈川(横浜) 千葉 埼玉 東横線沿線を中心に離婚協議書の作成をさせていただきます。
公正証書の作成もお手伝いさせていただきます。
財産分与の期限
1.財産分与の請求期限
財産分与については、請求に係る期限があるので注意が必要です。
即ち、財産分与の権利は離婚が成立してから丸2年と定められています。(※民法第768条2項)
※民法第768条
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
仮に離婚後、ずいぶん経過してから相手の隠し財産が発覚したとしても、財産分与を求めることはできません。
逆に離婚時に財産分与をしなくても、離婚から2年以内であれば、財産分与を請求することが可能です。
ただし、離婚時に離婚協議書を作成の上、清算条項(「今後一切財産上の請求をしない」のような文言)を入れたような場合、請求できなくなります。
2.2年経過後の財産分与
前項で財産分与は2年以内に請求といいましたが、これは当事者間の協議が整わない場合に、家庭裁判所に対し協議に代わる処分を請求する期限が2年以内なのであって、当事者同士が合意で財産分与に関する合意をすることに期限はありません。
ですので、離婚後2年経過後に財産分与請求し、相手が拒否した場合には財産分与は認められませんが、相手がこれに応じ、財産分与について合意が出来れば財産分与は可能と解されています。
ただし、離婚後2年以上経過してから財産分与をすると、外形的には財産分与か贈与か区別がつきません。
通常財産分与には課税はされませんが、税金逃れのために贈与を財産分与と偽っていると判断されてしまうと贈与税が課される可能性も否定はできません。
離婚後2年以上経過してから財産分与をする場合、財産の移転が財産分与によるものであると証明できるよう、しっかりとした協議書(特に公正証書)を作成するなどして対応することになりますが、最終的な判断をするのは税務署ということになります。
そのため、財産分与はなるべく離婚後2年以内に行うことをお勧め致します。
後悔しない離婚のために、女性行政書士が親切丁寧な対応をさせていただきます。
東京 神奈川(横浜) 千葉 埼玉 東横線沿線を中心に離婚協議書の作成をさせていただきます。
公正証書の作成もお手伝いさせていただきます。
財産分与の方法
財産分与はどのように進めるのでしょう。
協議、調停・審判、裁判が考えられますが、
まずは、夫婦の話し合い(協議)で取り決めることになります。これが一番早くて簡単かと思います。
財産分与の方法としては、
(1) 不動産や自動車等対象財産の全てを一方が取得する代わり、相手方に金銭を渡して清算する
方法。
(2) 対象財産を売却し、得られた利益を分ける方法。
(3) 財産ごとにどちらが取得するか決める方法。
さまざまな方法があります。
また、財産分与は婚姻期間中に協力して形成した財産を2分の1の割合で清算するのが原則であるとお伝えしましたが、当事者が納得さえすれば、2分の1に限らず、どのような割合で清算しても構いません。
夫婦で協議の上合意が得られた場合には、その内容を記載した離婚協議書を作成することが一般的です。
また、分割払い等、将来にわたって支払が継続する場合には、支払が滞る危険性もありますので、給与や財産の差押え等がすぐにできるよう、強制執行認諾条項付の公正証書を作成しておくことをお勧め致します。
当事者の話し合いでまとまらない場合には、離婚調停、離婚審判、離婚訴訟といった裁判所の手続を通して決めていくことになります。
後悔しない離婚のために、女性行政書士が親切丁寧な対応をさせていただきます。
東京 神奈川(横浜) 千葉 埼玉 東横線沿線を中心に離婚協議書の作成をさせていただきます。
公正証書の作成もお手伝いさせていただきます。
財産分与~債務
これまで述べてきたとおり、財産分与の対象、割合については、基本と当事者間の協議で自由に決めることが可能です。
債務を含めるか否かも協議次第です。
ただ、当事者間での協議が整わない場合、裁判所で決めることになりますが、裁判実務においてどのように考えているかというと以下のとおりです。
清算的財産分与とは、離婚時に存在する積極財産を清算する制度です。
なので、積極財産がなく債務(消極財産)だけ、という場合には、分与すべき財産がなく、債務そのものが財産分与の対象になることはありません。
しかしながら、積極財産と債務の双方がある場合、公平という観点から、財産分与の中で債務を考慮すべき場合があります。
①資産形成のために生じた債務
例えば、居住用不動産を取得するために負担した住宅ローンが典型です。住宅や自動車等積極財産を形成するために負担した債務は、公平という観点から、当該財産を分与する過程で債務も考慮されることになります。
また、夫又は妻が、個人で事業を営んでいて、積極財産がこの事業によって形成されたという事情がある場合には、公平という観点から、事業で負った債務も考慮されることになります。
②結婚生活のために必要であった債務
例えば、生活費、医療費のために負った借金や子の教育費用を捻出するために負担した教育ローンなどは、財産分与に際し考慮されることになります。
これに対し、当然ながら、結婚前に個人的に借り入れた借金は財産分与の対象にはなりません。
また、結婚後に負担したものであっても、ギャンブルや趣味、奢侈品を購入するための債務については、財産分与の際に考慮されません。
さらに、結婚前であっても結婚後であっても、相続で得た債務は考慮されません。
夫婦共同生活の為に負った債務か否かというのが判断のポイントでしょうか。
後悔しない離婚のために、女性行政書士が親切丁寧な対応をさせていただきます。
東京 神奈川(横浜) 千葉 埼玉 東横線沿線を中心に離婚協議書の作成をさせていただきます。
公正証書の作成もお手伝いさせていただきます。
財産分与~居住用不動産
ご自宅の不動産は財産分与に際して特に問題になります。
離婚の際に、一番大きな問題となるのがこの不動産といえるかもしれません。
婚姻生活が長いとローンを組んで不動産を購入されるご夫婦も多いかと思います。
先述のとおり、例えこの家の名義がご主人様の単独名義になっていて、ご主人様が単独でローンの返済をしているような場合でも、奥様に潜在的な持分はあります。
不動産については以下不動産を売却する場合、しない場合の二つのケースが想定されます。
1.不動産を売却する
この不動産を売却し、その売却代金から、住宅ローンの残債務を弁済し、諸経費等を差し引き、残った金額を夫婦で分配する。これが一番合理的で明確な方法と言えるかもしれません。
しかし、売却して、利益が出ればいいのですが、残念ながら損をするケースもあります。仮に損をしてしまうことになっても、とにかく夫婦関係をきれいに清算して、トラブルの種を残さないことが第一と考えるなら、やはり売却することが一番かもしれません。
この場合、基本的に財産分与の対象となるのは積極(プラス)財産のみなので、ローンが残ってしまった場合はローンの名義人が負担するというのが実務です。
ただ、公平という観点で考えれば、マイナスが出ればそのマイナスも負の財産として夫婦分けあって負担するということになります。このあたりは夫婦の合意次第となります。
2.不動産を売却しない
不動産を売却できない場合や、いずれか一方が住み続けることを希望する場合は不動産を売却しないという選択ももちろんあります。
この場合、ローンがある場合、ない場合で以下のようなパターンがあると思います。
①ローンがない場合
住宅ローンがない場合、公平という観点からすると、不動産の価値を算出し、それを2分の1の割合で清算することになります。
不動産を取得する側が取得しない側に対し、清算金として不動産価格の2分の1の額を支払うというのが一般的です。
もちろん当事者の合意次第で清算割合等、如何様にも取り決めることが出来ます。
②ローンがある場合
以下典型的なケースで検討してみます。
ア.夫が取得して住み続ける場合
夫がローンの単独債務者で、夫が今後も住宅に住み続ける場合はさほど問題はないでしょう。
この場合、夫は、不動産の価格から住宅ローンの残債務額を差し引き、プラスがあればそのプラス分の2分の1の価格を妻に清算金として支払うというのが一般的でしょうか。
マイナスになるようであれば、妻に清算金を支払う必要はなく、夫がそのまま住宅ローンを支払っていくことになります。
問題なのは妻が連帯債務者、連帯保証人になっているケースです。
共働きの夫婦も増えている昨今ですが、最近では「ご主人の年収だけではローンを組むのは無理ですが、奥様の収入も足すことによって十分買えますよ。」等といい、住宅ローンの貸付をしたがる金融機関も増えているようです。
夫婦共にローンを組むことも、夫婦関係がうまくいっているときはいいのですが、一旦夫婦関係が悪くなってしまい、離婚することになると大変です。
銀行と協議し、妻を連帯債務者、連帯保証人から外してもらえれば一番よいのですが、連帯債務者、連帯保証人は人的担保です。
新たな連帯保証人などを立てない限り銀行はそう簡単には応じてくれないことでしょう。
このため、当事者間で、夫が住宅を取得し、残りの住宅ローンも全部引き受けると合意することがあります。
確かに当事者間で、このような合意することは可能です。
ただこれはあくまで当事者間での話であって、銀行との関係では妻が連帯債務者、連帯保証人であることに変わりありません。
将来夫がローンの支払いを怠れば、銀行は当然のように妻に請求をしてきます。
このことを念頭において、万一夫が支払いを怠った場合に備え、公正証書等で詳細に取り決める必要があるでしょう。
イ.妻が取得の上妻が住み続け、住宅ローンも夫名義から妻の名義にするケース
住宅の名義を妻にして、住宅ローンも妻が引き受ける場合、妻にそれなりの収入が必要になります。新たに妻が金融機関の住宅ローン審査をクリアできれば良いのですが、専業主婦やパートしかしていない場合、難しいといえるでしょう。
ウ.妻が取得し妻子が離婚後も住み続けるが、住宅ローンは夫が支払い続ける場合
離婚後、子供の学校の関係から、住宅を妻に財産分与してもらい、妻と子供がそのまま住み続け、住宅ローンは元・夫に支払い続けてもらう、という希望をお持ちの方も多くいらっしゃると思います。
夫婦間で合意が出来れば、財産分与として妻が不動産を取得することは可能です。
ただ、住宅ローン返済中に家の名義を変更する場合、ローンを組んでいる銀行との関係で注意が必要です。
住宅ローンの約款をよく読むと、「ローンの支払期間中に名義を変更する場合は、まず金融機関に連絡して承諾を得てください」「承諾を得ずに名義を変更した場合は、ローンを一括請求することがあります」といった内容の条項が入っていることがあります。
また、ローンの名義人(債務者)が当該不動産に居住することを要件としていることもあります。この点からも、銀行の承諾を得る必要があるでしょう。
ただ、銀行はなかなか承諾をしてくれません。ローンの債務者と住宅の所有者が異なるのは好ましくないからでしょう。
銀行の承諾を得ず登記名義を変更しても、ローンの返済がしっかりなされ、滞納などがない場合、銀行は気が付かないかもしれませんが、万一銀行に知られたら契約違反として残りのローンを一括請求されてしまう可能性がないわけではありません。
銀行が強硬手段に出ることを想定しておく必要があります。
そこで、銀行の承諾を得た上、住宅ローンの債務者は夫のまま、ローン完済後に不動産の名義を妻に移すという方法がとられることがよくあります。
財産分与~宝石、バッグ、時計
指輪等の宝石や、バッグ、時計等は財産分与の対象財産になるのでしょうか?
結論からいいますと、基本ならないけれど、例外的になる場合があるということになります。
この点、宝石、バッグ、時計等については、通常夫婦が共用することは想定されておらず、どちらか一方の専用になることが想定されています。
このように、どちらか一方だけが使用することを予定して購入された財産を専用財産といいますが、専用財産は特有財産ということになり、通常は財産分与の対象にはならないということになります。
しかしながら、高額のものについては、それが財産分与の対象にならないと不公平な結果となる場合があります。
例えば、最近エルメスやシャネルのバッグの価格は高騰しており、1個数百万の価値のあるものもあります。
宝石やローレックスの時計も同じです。
専用のものでも、数個持っているだけで1000万円を超すこともあります。
このように、たとえ専用のものでも、高価なものについては、財産分与の対象財産として検討する場合があります。
この点、裁判所の判断はどうなっているのかといいますと、ダイヤモンドの指輪とサファイアの指輪の合計80万円を財産分与の対象財産とした裁判例(東京高判平7.4.27)と、1点が30万円から80万円の宝石類3点について財産分与の対象外とした裁判例(名古屋家審平10.6.26)があります。
ケースバイケースということでしょうか。
夫婦がそれぞれ同じくらいの価値の物を所有しているのであれば問題ないかもしれませんが、一方は宝石やバッグを多数所有し、一方はまったくない、その他分けるような財産もないということになりますと不平等な結果になります。
公平という観点から検討する必要がありそうです。
後悔しない離婚のために、女性行政書士が親切丁寧な対応をさせていただきます。
東京 神奈川(横浜) 千葉 埼玉 東横線沿線を中心に離婚協議書の作成をさせていただきます。
公正証書の作成もお手伝いさせていただきます。
財産分与~保険、年金
1.生命保険
生命保険については、離婚時の解約返戻金の額を対象とします。
結婚前の保険料の支払がある場合は、婚姻時の解約返戻金の額が分かればこれを離婚時の額から差し引き、分からなければ契約期間内の同居期間で按分することになります。
2.年金
(1)厚生年金
離婚時年金分割制度が創設されたので、財産分与の中で考慮する必要はなくなりました。
(2)確定拠出年金
確定拠出年金とは、老後の資産形成を目的にした私的年金です。
拠出された掛金とその運用益との合計額をもとに、将来の給付額が決定する年金制度です。
掛金を事業主が拠出する企業型DC(企業型確定拠出年金)と、加入者自身が拠出するiDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)があります。
①企業型DC(企業型確定拠出年金)
確定拠出年金制度を導入している企業が実施する確定拠出年金で、企業に在籍する従業員が対象者です。
将来給付する額をあらかじめ決めた上で、その給付額をまかなうために企業側が掛け金として拠出し、従業員本人が運用を行います。
確定拠出年金の掛け金は、退職金の前払いのような性格を有していることがうかがえます。
②iDeCo(以下、個人型確定拠出年金)
個人の加入者が自分で掛け金を拠出し、運用を行います。みずから掛け金を決めて、個人の責任で運用するものです。
「個人型」は、自営業者、公務員を含む厚生年金保険の被保険者、専業主婦等、公的年金制度に加入する60歳未満の全ての人が加入対象となっています。自身で掛金の積立て・運用を行い、老後の資産を形成する年金としての性格を有します。
かけ金を自ら拠出していることから貯蓄に近いといえます。
確定拠出年金は、資産形成という側面もあることから、財産分与の対象になる可能性があります。
ただし、財産分与というのは、婚姻中に協力して形成した財産を離婚時に清算するという趣旨であることから、その対象となる財産は、婚姻期間中に形成したものに限られます。そのため、仮に確定拠出年金が財産分与の対象となるとしても、原則として、あくまで婚姻期間中の掛金相当の部分が対象になります。
確定拠出年金が財産分与の対象となるかはこちらを参照⇒離婚Q&A 確定拠出年金
(4)個人年金
個人年金は、保険会社や銀行、証券会社が販売する保険商品、金融商品であり、その内容は、貯蓄的なものから、老後保障的なものまで様々ですが、一般の保険契約と同様、離婚時(又は別居時)における解約返戻金が財産分与の対象になります。
扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚によって夫婦のどちらか一方の生活が困窮する場合に、経済的余裕がある一方が他方の配偶者に対し、一定期間の生活費相当額を支払うものです。
離婚が成立しますと、扶養義務はなくなりますので、一方が他方の生活費を負担する必要はなくなります。
仮に妻が専業主婦で、主に夫の収入で生活していた場合でも、夫は、離婚後子の養育費の支払義務はありますが、妻の生活費を支払う義務はなくなります。
ただ、これまで専業主婦であった妻がいきなり職に就けるかといとそうは簡単にいかないかと思います。小さい子どもがいるとなるとなおさらです。
そのような場合に、離婚後一定期間、離婚により経済的不利な立場に立つ一方に対して、他方から支払われるのが扶養的財産分与なのです。
離婚時の財産分与については、婚姻期間中に協力して形成した財産を清算するという清算的財産分与がメインであり、実務上は、扶養的財産分与はかなり例外的な場合にしか認められません。
清算的財産分与や慰謝料があっても、なお生活に困る場合に認められるという補充的なものです。
以下のようなケースの場合、扶養的財産分与が認められることが多いようです。
一方が長年専業主婦ですぐには仕事に就けない
一方が病気で生活が困窮するおそれがある
熟年離婚により、高齢のため仕事に就くことができない
協議離婚においても、当事者間で合意ができれば、扶養的財産分与を取り決めることができます。
扶養的財産分与の内容
扶養的財産分与の要否や額、期間はどのような点を考慮して決めるのでしょうか。
この点について参考になる裁判例があります。
名古屋高決平成18年5月31日
「夫婦が離婚に至った場合、離婚後においては各自の経済力に応じて生活するのが原則であり、離婚した配偶者は、他方に対し、離婚後も婚姻中と同程度の生活を保障する義務を負うものではない。しかし、婚姻中における生活協同関係が解消されるにあたって、将来の生活に不安があり、困窮するおそれがある配偶者に対し、その社会経済的な自立等に配慮して、資力を有する他方配偶者は、生計維持のための一定の援助ないし扶養をすべきであり、その具体的内容及び程度は、当事者の資力、健康状態、就職の可能性等の事情を考慮して定めることになる。」
この裁判例等を参考にすると、
扶養的財産分与については、義務者の収入、財産状況、扶養義務を負う親族の存否、有責性の有無
要扶助者の生活状況、財産状況や健康状態、就職の可否、年齢等を考慮することになるようです。
なお、期間については、1年から5年とするものが多いようです。
要扶養者が自活できるまでの期間というのが一つの基準になり、要扶養者の年齢、仕事をしていなかった期間、能力、資格の有無などから就労の可能性を検討していくことになろうかと思います。
若ければ短くなり、高齢の場合は長くなる傾向にあり、10年から20年になるケースもあるようです。
後悔しない離婚のために、女性行政書士が親切丁寧な対応をさせていただきます。
東京 神奈川(横浜) 千葉 埼玉 東横線沿線を中心に離婚協議書の作成をさせていただきます。
公正証書の作成もお手伝いさせていただきます。
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日
<離婚相談・遺言・相続>
神奈川県横浜市の「行政書士藤縄純子事務所」では、担当の女性行政書士が東京都内、神奈川県を中心に、離婚相談や遺言・相続のお手伝いをしております。
離婚協議書、婚前契約書、事実婚契約書、夫婦間契約書の作成を代行しております。また、相続のご相談や、遺産分割協議書・遺言書などの公正証書作成のお手伝いも承っております。
親切丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にお問合せください。
| 対応エリア | 東京23区:世田谷区・杉並区・大田区・目黒区・品川区・新宿区・渋谷区等。その他:調布市・狛江市・三鷹市・府中市・町田市、京王線・小田急線沿線や横浜市等が中心ですが、 書面の作成のみでしたら全国対応です。 |
|---|
お気軽にお問合せください
お役立ち情報
不倫・不貞
男女問題
夫婦関係
事実婚・内縁関係
相続・遺言
その他のサービス
事務所紹介
離婚と税金
<業務エリア>東京23区:世田谷区・杉並区・大田区・目黒区・品川区・新宿区・渋谷区等
その他:調布市・狛江市・三鷹市・府中市・町田市、京王線・小田急線沿線や横浜市等が中心ですが、
書面の作成のみでしたら全国対応です。